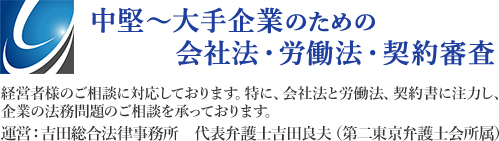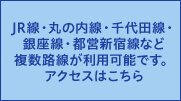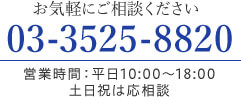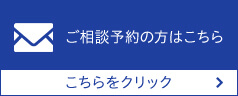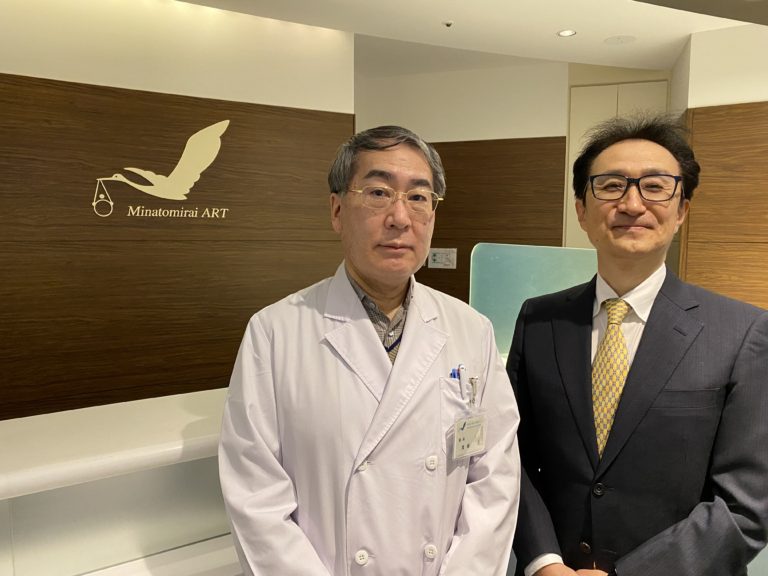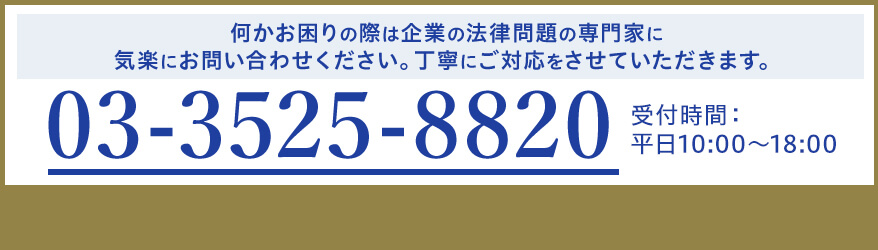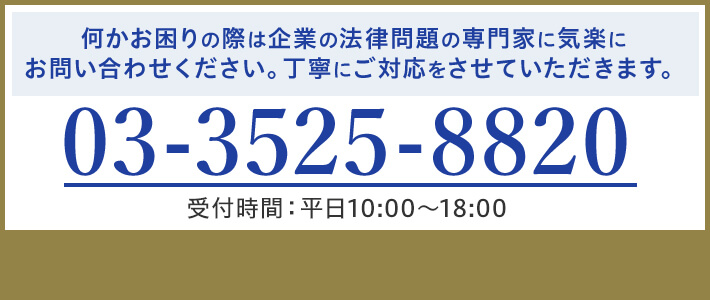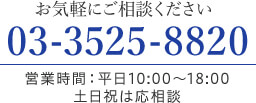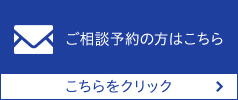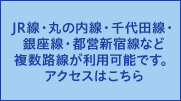令和5年6月に成立した改正不正競争防止法の内容とは?
令和5年6月に、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この改正法は、不正競争防止法や商標法などの知的財産に関する法律を改正するものです。
特に不正競争防止法は、営業秘密が侵害された事件が度々報道されるようになってきていることから、注目されるようになってきています。
また、転職が当たり前の社会となり、営業秘密等が漏えいしてしまう抽象的な危険性が高まっていることもありますので、不正競争防止法を知っておくことは企業の利益を守ることに繋がります。
そこで、本記事では、不正競争防止法の令和5年改正の内容を解説いたします。
不正競争防止法の営業秘密とは?
大手回転寿司チェーン店を運営する会社の前社長が営業秘密を不正に持ち出したとして不正競争防止法違反の罪で逮捕されたという報道がありました。
営業秘密の侵害については、不正競争防止法という法律が、民事責任(損害賠償請求や差止請求など)や刑事責任(懲役刑や罰金刑)を定めています。
そして、近年は、この事件のように企業から営業秘密が漏えいして民事裁判や刑事裁判となることが増えています。
営業秘密の侵害行為とは?
不正競争防止法は、営業秘密侵害行為を細かく定めていますが、以下の3類型があります。
- 営業秘密保有者から不正に取得したことに起因して、点々流通する過程で行われる不正取得類型
- 当初は適法に開示を受けた営業秘密が、その後に不正に使用・開示され、その後点々流通する過程で行われる信義則違反類型(不正開示型)
- 侵害品譲渡等類型
3類型それぞれについて、第一次取得者と第二次取得者(転得者)の行為が営業秘密侵害行為として規定されています。
中小企業・中堅企業が気を付けるべき独占禁止法とは?
独占禁止法は大企業を取り締まる法律なので、中小企業・中堅企業には関係ないと思われている経営者も多いのではないでしょうか。
実際のところ、下請法には注意している中小企業・中堅企業であっても、独占禁止法まで意識が向いている方はそれほど多くないと思われます。
しかし、中小企業・中堅企業であっても、知らず知らずのうちに独占禁止法に違反してしまうこともありますので、注意(リスクマネジメント)が必要です。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」とは?独占禁止法上の優越的地位の濫用と下請法上の買いたたき
令和5年11月29日に、内閣官房及び公正取引委員会から、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(以下、「本指針」といいます。)」が公表されました。
本指針は、公正取引委員会が行った、「令和5年度独占禁止法上の『優越的地位の濫用』に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」を踏まえて、労務費の転嫁に係る価格交渉について、発注者と受注者が採るべき行動・求められる行動をまとめたものです。
インボイス制度の開始に伴い注意すべき独禁法・下請法とは?
2023年10月から開始されるインボイス制度に伴い、企業は取引先である免税事業者との取引条件を見直す可能性があります。
もっとも、免税事業者は売上1000万円以下の小規模事業者であり、一般的に交渉力が弱く、取引条件が一方的に不利になりやすいので、企業は免税事業者との取引条件の交渉の際は、独占禁止法上の優越的地位の濫用や下請法に違反しないよう、注意しなければなりません。
そこで、企業がインボイス制度を契機として免税事業者との取引条件を見直す際に注意すべき点を見ていきます。
令和5年10月1日施行のステルスマーケティングに対する規制とは?
今回は、企業様の業務に影響があるかもしれない、ステルスマーケティング規制について情報提供いたします。
消費者庁は、ステルスマーケティングに対する規制として、景品表示法第5条3号に基づき指定を行い、指定の運用基準を公表しました。
特定商取法の改正① 申し込み時の表示規制とは
今回の改正法によって、規制対象が広がり、新たに対応が必要となる企業様もおられます。しかし、今回の改正法の内容は非常に細かく複雑で、消費者庁が公表している資料も、量が多くて読み解くにも時間がかかります。
当事務所では、顧問先の企業様から問合せを受けたこともあり、消費者庁の担当者による有料の解説講義を受講し、消費者庁の公表資料を検討するなどして、改正法の内容をQ&A方式でまとめました。
より多くの企業様のご参考になればと思い、ここで紹介いたします。
特定商取引法の改正② 申込時の表示規制・不実告知とは?
特商法第12条の6第2項で販売業者や役務提供事業者の一定の表示が禁止されたと聞きましたが、規制の内容はどのようなものでしょうか?
2022年道路交通法改正~白ナンバー車使用事業者のアルコールチェック義務化へ~
近時、飲酒検査に関する道路交通法の改正についてご質問をいただく機会があり、道路交通法及び同施行規則を確認しました。事業を行う方々に広く関係する法改正ですので、ご紹介します。
刑事事件の流れとは?
連日のニュースで、「凶悪事件が発生しました。」、「犯人が逮捕されました。」、「重大事件の裁判が行われました。」と報道されています。
このようなニュース報道を見ている方のほとんどは、他人事として見ており、まさか自分が当事者になるということは考えてもいないでしょう。しかし、その日は突然やってきます。