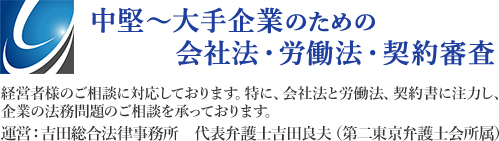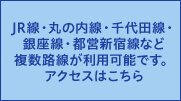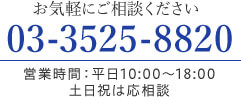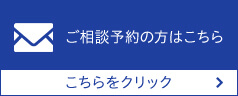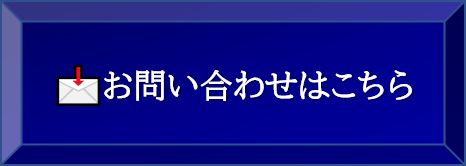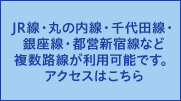| 【目次】 1 事業承継のための株式譲渡とは? 2 遺留分とは?1年前の贈与も対象になる? 3 対価を支払う株式譲渡(売買契約)であれば遺留分の対象にならない? 4 経営承継円滑化法は利用できる? 5 事業承継のための株式譲渡でお困りの際は吉田総合法律事務所にご相談ください |
1 事業承継のための株式譲渡とは?
中小企業・中堅企業を後継者に事業承継する場合、会社の経営権(支配権)を後継者に確保させることが必要になります。
一般的には、現経営者(以下「先代経営者」といいます。)が保有する株式を経営承継者(新経営者)に移動させることにより、新経営者が経営権(支配権)を確保するパターンが多いと思います。
しかし、新経営者に株式を移動させた先代経営者が亡くなり相続が発生した時に、民法の遺留分規定によれば、新経営者が先代経営者の相続人から遺留分侵害額請求をされるという想定外の事態が起きるかもしれません。
その場合に、新経営者が遺留分侵害額として支払う額が高額になれば、新経営者個人の財産的安定性が損なわれ経営全体に悪影響が起きるかもしれませんし、先代経営者の相続人と新経営者の対立は企業の社内社外の混乱の引き金になるかもしれません。

特に親族外承継(先代経営者とは血縁関係のない会社の取締役に、新経営者になってもらうパターンが典型的です)の場合には、上記リスクも考える必要があります。そこで、「備えあれば憂いなし」のために本記事をご検討いただき、万一のリスクにも十分な対策を講じて、「安心できる事業承継」を実現していただきたいと思います。
2 遺留分とは?1年前の贈与も対象になる?
遺留分は、一定の範囲の相続人に対して、一定の割合による最低限の相続権を保障する制度です(民法第1042条以下)。
亡くなった方(以下「被相続人」といいます。)が生前に第三者に財産を贈与していたり、遺言で財産を第三者に遺贈したりして、相続人に最低限保障されている遺留分が侵害されてしまった場合には、相続人は、生前贈与や遺贈を受けた第三者に対して侵害された遺留分を請求することができます。
民法では、遺留分を計算する際の財産額は、相続開始時に被相続人が有していた財産(相続財産)と、相続開始前の1年間に贈与された財産、遺留分権者(相続人)に損害を加えることを知って贈与された財産(この場合は期間制限がありません。)を合計したものと定めています。
事業承継の場面で見ると、先代経営者から新経営者へ株式を無償で贈与した場合、それが相続開始前の1年間でなされたものであれば、民法第1044条1項により譲渡された株式も遺留分を計算する際の財産に含まれることとなり、遺留分の対象となってしまいます。
また、相続開始前の1年間でなかったとしても(1年以上前になされたものであったとしても)、遺留分権利者(相続人)に「損害を加えることを知ってなされた」ものであれば、同様に遺留分の対象になってしまいます。
なお、遺留分の問題が生じるのは、事業承継の相続の場面に限られたものではありません。
経営者ではない株主が生前に株式を譲渡(または贈与)する場合にも遺留分の問題が生じることはありますし、株式ではなく金銭や不動産を譲渡(または贈与)する場合にも遺留分の問題が生じることはあります。
本記事は、経営者の事業承継の相続という場面での遺留分の問題を取り上げていますが、遺留分の問題はこの場面に限られるものではないということにご注意ください。

3 対価を支払う株式譲渡(売買契約)であれば遺留分の対象にならない?
⑴ 対価が不相当な場合には遺留分の対象になってしまうリスクがある
民法の遺留分の規定によれば、無償での贈与だけでなく、対価を支払う株式譲渡(株式の売買契約)であっても、遺留分の対象になる可能性(リスク)があります。
民法第1045条2項は、対価を支払うものであっても、その対価が不相当な対価であり、それにより遺留分権利者(相続人)に損害を加えることを知っていた場合には、その差額分について遺留分の対象になると定めています。
この民法第1045条2項は、客観的要件と主観的要件に分けて考えることができます。
客観的要件である「不相当な対価」は、株式譲渡(株式の売買契約)であれば株式譲渡時の取引価格を基準として判断されます。
主観的要件である「遺留分権者に損害を加えること知っていた」とは、遺留分を侵害する認識があれば良く、損害を与えるという加害の意図までは必要ありません。そして、遺留分を侵害する認識が認められるためには、相続開始時までに財産に何らの変動のないことを予見していたことが必要であるとされています。
⑵ 対価が不相当であるか否かはどのように判断するのか
この民法第1045条2項により、対価を支払う株式譲渡(売買契約)により事業承継した場合であっても、その対価が不相当な対価である場合には、相続人から遺留分侵害額請求をされてしまう可能性があるということになります。
それでは、客観的要件である「不相当な対価」はどのように判断したら良いでしょうか。
上場企業であれば株価がマーケットで決まりますが、非上場企業の株式譲渡の際の株式価格(株価)の算定方法は多数の方法があり、課税面で算定するのか、企業価値面で算定するのかによって、適用する算定方法が異なることが通例です。
当事務所で文献及び裁判例をリサーチしましたが、株式譲渡(株式の売買契約)の際に遺留分規定の「不相当な対価」の算定方法(例えば時価純資産法か、簿価純資産法か、類似業種比準法か、配当還元法か、DCF法か、それ以外の方法か等)について、明確な記載をしたものは見当たりませんでした。つまり、遺留分規定の「不相当な対価」は株式譲渡の場合にはどの方法により判定されるのかという問題は議論すらされていない状況であると思われます。
⑶ 「不相当な対価」に関する裁判例の紹介
ここで当事務所がリサーチした裁判例をご紹介します。
被相続人が亡くなる約6か月前に株式を1株1円で譲渡したことについて、相続人が不相当な対価による株式譲渡であり、遺留分を侵害すると主張して争われた事案です(この事案はその他にも多くの争点がありますが、株式譲渡の「不相当な対価」の点に限定して紹介いたします。)。
東京地方裁判所は、株式譲渡時の時価純資産法により算出した1株当たりの株価は5437円であることから、1株1円での株式譲渡は、不相当な対価によるものであると判断しました(東京地裁令和3年9月13日判決(判例集未掲載、事件番号:平成29年(ワ)第29285号))。

この裁判例では、なぜ時価純資産法により株価を算出するのかという点について、何ら言及しておりませんので、他の事案でも必ず時価純資産法で算出しなければならないわけではないと考えられます。
なお、この事案では、この株式譲渡により遺留分権利者に損害を加えることを知っていたとはいえないとして、結論としてはこの1株1円での株式譲渡は遺留分の対象にはならないと判断されました。
⑷ 紛争化のリスクは完全には防止できない
上記の次第であり、「不相当な対価」の論点について踏み込んだ記載はできないのですが、おそらく課税面で問題のない算定方法であれば、「不相当な対価」であるという認定はされにくいのではないか、と推察しております(ただし、文献に記載のない実務上の論点ですから、当事務所は一切の法的及び非法律的責任を負わないことを明示的に記載します。)。
したがって、事業承継のために株式譲渡を行う場合には、(事案によりけりではありますが)相続発生後に新経営者が相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクが完全には消滅しない、こともあると言わざるを得ません。
なお、民法第1045条2項で問題となるのは、不相当な対価で行われた株式譲渡等によって遺留分が侵害された場合です。
仮に株式譲渡等が不相当な対価で行われたとしても、それにより遺留分が侵害されなければ、民法第1045条2項の問題は生じません。
そのため、株式譲渡等を行う際には、将来の相続発生時に遺留分侵害となるか否かも十分に検討する必要があります。
4 経営承継円滑化法は利用できる?

このような遺留分の問題に対処するために、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「経営承継円滑化法」といいます。)が制定されました(経営承継円滑化法の概要は中小企業庁のサイト でご確認ください。)。
経営承継円滑化法は、遺留分に関する民法の特例を規定しており、これを活用することで、経営承継(事業承継)の際の遺留分の問題に対処できると言われています(立法の狙いです)。
しかし、経営承継円滑化法は、事業承継のための株式譲渡により後継者が取得した株式等を遺留分の対象から除外することなどについて、相続人となる者(推定相続人)全員と後継者の合意を求めております。
他方で現実を見ますと、相続発生後に相続人から遺留分侵害額請求を受けるような事案では、そもそも相続開始前から後継者と先代経営者の推定相続人が対立してしまっていることが少なくなく、合意が得られないことが多いと思われます。
また同法は手続きが複雑なため、利用数が少ないという実情があります。
そのため、事業承継(特に親族外承継)に経営承継円滑化法が利用できるケースは限られている(実際はとても使いにくい)と言わざるを得ません。
5 事業承継のための株式譲渡でお困りの際は吉田総合法律事務所にご相談ください
事業承継は、会社にとっても、先代経営者にとっても、新経営者にとっても、一大事業です。
問題なくスムーズに事業承継を行いたいと誰もが考えるものです。

他方で、相続のときは親子や兄弟姉妹(相続人)ですら紛争になってしまう(相続が「争族」に、さらに紛争が長期化する「争続」になる。)ことは多々あります。いったん新経営者がこのような紛争に巻き込まれてしまうと、会社の経営にも少なからず影響が生じてしまいます。
また、紛争に巻き込まれることを恐れて、新経営者が見つからなくなってしまうことも考えられます。
このようなことを防止するためには、早い段階から専門家の適切な助言を受けて、株式譲渡を含めた総合的視点からの戦略的事業承継をプランニングして実践していくことが重要となります。
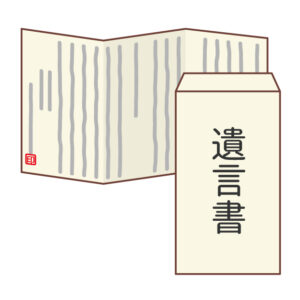
なお、遺留分の問題を法的に解決するものではありませんが、相続を発端とする紛争化を防止するためには、先代経営者が相続人に対して遺言書を作成し、子息子女、配偶者に、その遺言書を前提とした説明を生前に心を込めて行うことは、紛争予防に効果があることが多いです。
先代経営者の心が相続人(配偶者や子など)に伝われば、仮に遺留分侵害となる可能性があったとしても、先代経営者の気持ちや意向を尊重して、遺留分の請求をしない(紛争化しない)で円満な交渉その他の解決ができることもあり得ます。
吉田総合法律事務所の弁護士は、日頃から事業承継における株式譲渡に関する案件に携わっており、豊富な知識と経験を有しています。

そのため、相続人との紛争を可能な限り回避する方法を検討し、問題なく事業承継が行えるようサポートいたします。
事業承継のための株式譲渡でお困りの方やご検討中の方は、吉田総合法律事務所へご相談ください。