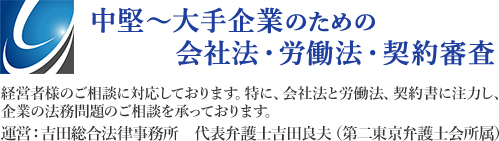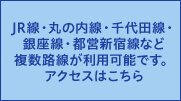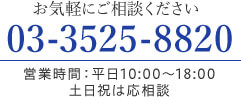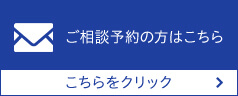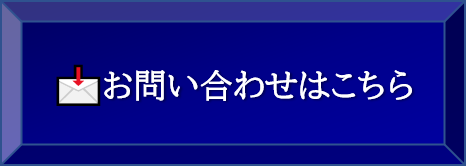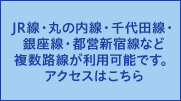会社と元代表取締役で訴訟をしたり、会社が現職の取締役と訴訟をする、いわゆる会社と役員間の訴訟では、会社を代表して裁判するのは代表取締役社長でしょうか? 監査役でしょうか? 実際に裁判提起をする、裁判に応訴する場合に大事な問題になります。
1 問題設定
原告のケースから説明します。
例えば、①退任した前社長が会社退任後に、会社財産を横領していたことが判明した、②会社からお金を借りた取締役が期限になっても弁済せず取締役会にも出てこなくなった、という事例で会社が裁判(訴訟提起)を検討中だとします。
これは会社が原告となって、前社長・元役員・現在の取締役・現在の代表取締役社長などに対し裁判を提起して法的請求をするパターンです。

これは、会社の代表取締役が会社を代表して裁判をするのか、監査役が会社を代表して裁判をするのか、弁護士に訴訟を委任する際に、委任状に記名押印するのは代表取締役か監査役か、どちらなのかという問題です。
被告のケースもあります。
退任した取締役が会社に対し法的請求をする場合にも同様の問題が生じます。
例えば、取締役任期中に取締役解任となったので解任の有効性を争う場合、または解任されたことにともなう損賠賠償請求をする場合(会社法339条2項)などのパターンです。
訴状に被告として記載されてあるのが、「A社代表取締役社長B」であっても、本当に代表取締役社長のBが会社を代表して本件訴訟を争うことができるのか、Bが弁護士に委任して裁判をすることができるかをしっかりと検討しないといけません。
もし会社を代表するべき者は代表取締役社長Bではなく、監査役Cであったなら、裁判所に上申書を提出して、原告に訴状訂正申立書を出してもらい訴状を訂正させる必要があります。
この問題は複雑な問題がありますので、すこし細かい話になりますが、お付き合いください。
2 会社代表権の一般論
会社法は、株式会社(以下単に「会社」といいます)を代表する権限については大要、次のような規定を置いています(以下では記事の分かりやすさのため要点を記載しています。正確な表現は条文をご確認下さい。)。
| <会社法> 349条4項 代表取締役が会社を代表する |

取締役会のある会社では、取締役会で代表取締役を定め、代表取締役(通常は社長)が対外的に会社を代表します。契約書にサインをするのが代表取締役であるのは、単に偉いからではなく会社の代表権があるからです。
3 会社と取締役間の訴訟の特則
会社法は取締役との訴訟について、次のような特則を置いています。
これは、一定の訴訟をする場合に、原則どおり代表取締役が会社を代表して裁判をすると、仲間意識や同情心理が働き問題があるだろう(手抜きをするかも知れない)という考えに基づきます。
| <会社法> 353条 会社と役員との間の訴えについて、株主総会は会社を代表する者を定めることができる。 364条 取締役会は、株主総会の定めがある場合を除き、会社を代表する者を定めることができる。 386条1項1号 会社に監査役がいる場合は、(349条4項、353条、364条の適用は排除され)監査役が会社を代表する。 |
この現行の会社法の規定だけを見ると、監査役がいる会社の場合、会社を代表するのは監査役のようにも読めます。

しかし、2006年5月1日より以前から存在している中小企業の場合、会社法改正に関連して、更にもう一捻り規定があります(ここが本記事で書きたかったところです)。
4 監査役が代表しない場合(386条の特則が適用されない場合)
(1)平成18年以前
会社法制定前、つまり商法の時代においては「小会社」という概念がありました。
(旧)商法特例法※1条の2は、次のように分類をしていました。
※正式名称は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」。会社法施行に伴い廃止されています。
| 大会社・・・①資本金の額が5億円以上、または ②最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上 小会社・・・資本金の額が1億円以下(上記②に該当するものを除く) |
この「小会社」は、会計監査人を置くことができず、監査役会設置会社にも委員会等設置会社にもなれませんでした。そんな大層な機関はその規模の会社には似つかわしくないと考えられていたものと思われます。
また、小会社の場合、監査役の監査権限が会計監査に限定されていました。昭和49年の商法改正により監査役の権限が会計監査だけでなく業務監査(取締役の職務執行全般の監査)にも拡大されましたが、小会社の監査役の権限は会計監査に限定されたままでした。
(2)平成18年以降
2006年(平成18年)に、これまで商法の中に規定されていた会社関係の事項は、新しく「会社法」として別個独立の法律として制定され、またこの際に会社を取り巻く制度が抜本的に改正されました。
従来の商法上の会社を、新会社法で扱う際の細かいルールを定めたのが会社法整備法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)です。
会社法整備法53条は、「旧小会社」の場合はこの会計限定の定め(会社法389条1項の定め)があるものと「みなす」と規定しました。
そのため、会社の定款上、監査役の監査範囲を会計に限定すると書いていない場合でも、会社法整備法により実際には「監査役の監査範囲が会計に限定」されていると「みなされる」といういわば落とし穴が生じることになります※。
※小会社が公開会社の場合は、公開会社でない会社を前提とする389条1項と矛盾するため、会計限定とみなされることはありません。ただ、中小企業で公開会社である会社は実際にはほとんどありませんので本論では触れておりません。
逆に、会社法は、公開会社ではない一定の会社は、定款で定めることにより監査役の範囲を会計に限定することができると定めています(会社法389条1項)。

つまり、会社法制定以降の会社(2006年5月以降に設立された会社)については、定款を見るだけで監査役の業務範囲を知ることができます。
(3)389条7項の定める適用除外
このような歴史的経緯もあり、会社法389条7項は、会計限定の定めのある株式会社につ
いては381~386条までの規定は適用しない、と定めています。
つまり、このタイプの監査役は、業務監査権限もなく(381条)、取締役会への報告義務(382条)や、取締役会への出席及び意見陳述の権利や義務もなく(383条)、総会への報告義務(384条)、取締役の違法行為の差止権(385条)もありません。

また、会社と取締役の訴訟における会社代表権(386条)もありません。
そのため、取締役会設置会社については、364条(会社を代表取締役が代表する)が適用され、監査役がいない会社と同様、取締役会が、株主総会の定めがある場合を除き、会社を代表する者を定めることができる、ということになります。
なお、取締役会が会社を代表する者を定めることが「できる」と定めていることについては、もし望むのであれば、定めることができるという意味に解されるため(商事法務「会社法コンメンタール8-機関(2)」234頁参照)、特に取締役会決議がない場合は代表取締役が会社を代表することになります。
5 まとめ
以上のとおり、監査役のいる会社は基本的には監査役が会社を代表して裁判をする(原告の場合)、監査役が会社を代表して裁判で応訴する(被告の場合)、ことになりますが、
- ①会計限定の定めがある会社、
- ②会計限定の定めがあるとみなされる会社
については、監査役ではなく代表取締役が訴え、応訴することとなります。
裁判の際にはこのあたりの事情についても気を配る必要がありますので、ご注意下さい。
会社が当事者となる裁判では、このように、手続きの面でも法的な知識が必要であり、注意しなければなりません。
そのため、会社が当事者となる裁判については、会社法に精通した弁護士に相談することをお勧めいたします。
吉田総合法律事務所の弁護士は、中小企業・中堅企業のお客様からのご相談を日々受け付けており、裁判対応も行っております。
会社が当事者となる裁判でお困りの方は、吉田総合法律事務所にご相談ください。