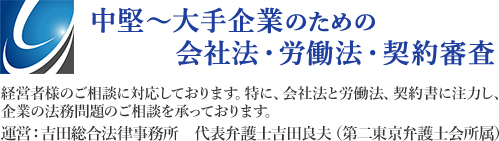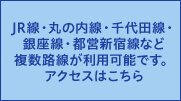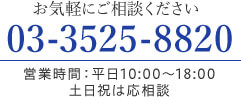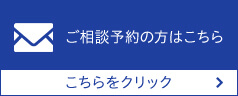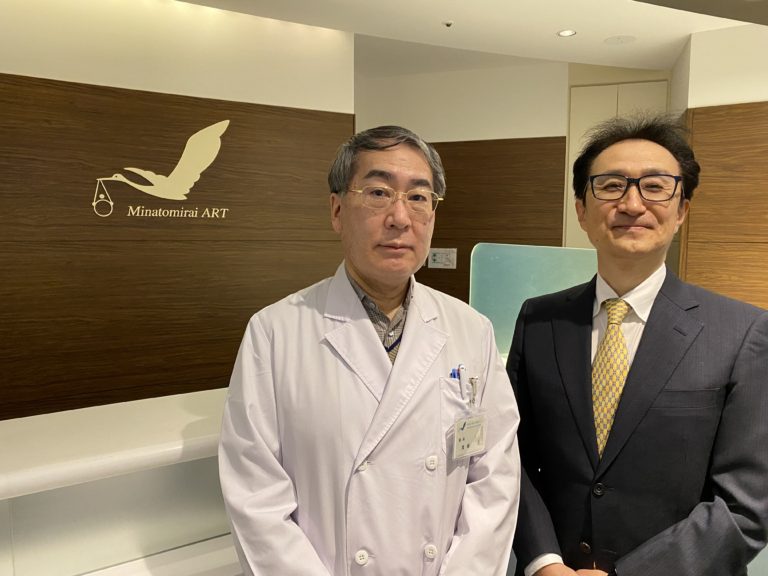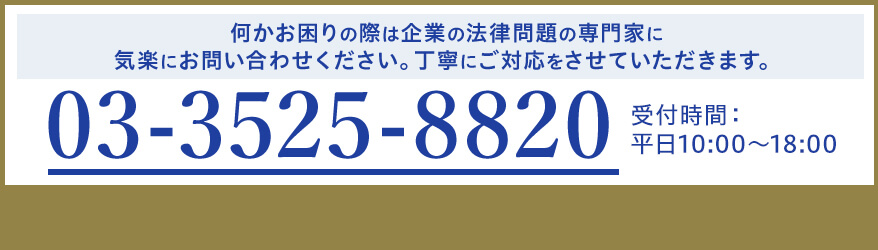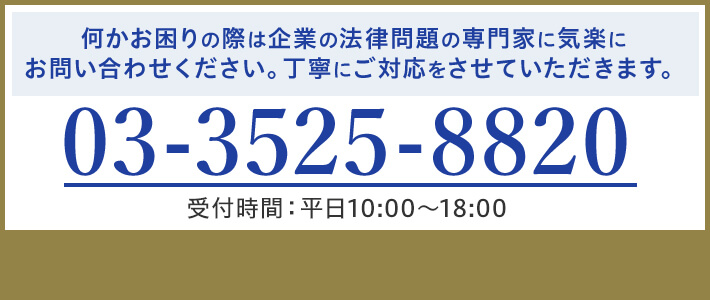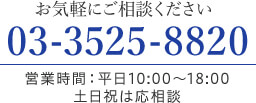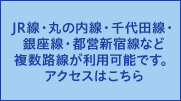| 【目次】 1 生成AIの普及と業務利用の拡大 2 生成AI利用による重大リスク! 3 契約書を生成AIに読み込ませる際の注意点 4 契約書作成やリーガルチェックでお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください。 |
1 生成AIの普及と業務利用の拡大
「生成AI」という言葉を、新聞やニュースで毎日のように目にするようになりました。
ChatGPTやGeminiなど一般に無料で使用することができる生成AIもあり、誰でも気軽に利用することができます。
また、その性能も向上しており、日々アップデートされています。
そのため、日常業務で利用する企業も増えてきているようです。
もっとも、生成AIを日常業務で使用する場合には、いくつか注意しなければならないことがあります。

便利な生成AIであっても、使い方を誤ってしまうと企業に損害が生じるなど、むしろマイナスとなってしまうこともあります。
そこで、本記事では、企業が日常業務で生成AIを使用する際の注意点について解説します。
2 生成AI利用による重大リスク!
生成AIの進歩はすさまじく、企業が日常業務で使用することができるほどの性能を持つものが出てきています。
そのため、日常業務で生成AIを使用する企業が増えてきており、しばらくすると生成AIを使用しなければ事業を行うことができなくなってしまうことになるかもしれません。
例えば、他社との取引に関する契約書のリーガルチェックを、生成AIを利用して行ったり、生成AIを利用して契約書を作成したりすることもできてしまいます(もっとも、リーガルチェックなどの正確性は定かではありません。)。
もっとも、生成AIは、AIが学習して進化するために、入力された情報やデータを保存する構造となっています。
また、入力した情報やデータを基に、他の企業等からの質問に回答することもあり得ます。

そのため、入力した情報やデータが、他の企業等に開示されてしまう可能性=情報漏えいのリスクがあります。
実際に、韓国の大手企業であるサムスン電子において、従業員が機密情報をChatGPTに入力してしまい、情報漏えいが発生してしまったということが起こりました。
サムスン電子では、このことが起きる前に、ChatGPTに入力する際には社内情報のセキュリティに注意して個人情報は入力しないことを通達していました。それにもかかわらず、このような情報漏えいが起きてしまったとのことです。
生成AIのような最先端技術は非常に便利ですので、上手く使いこなせば、業務効率の向上等に繋がります。
他方で、情報漏えいのリスクもあり、情報漏えいが発生してしまうと回復することが困難なものであることから、慎重な対応が必要となります。
生成AIを利用して契約書のリーガルチェックを行うのであれば、企業名等の特定情報、知的財産権やノウハウなどの機密情報はマスキングするなどして、社外に出しても問題のない状態にしなければなりません。
もっとも、マスキングすることなどをルール化しても、見落としのミスによって情報漏えいしてしまうことは考えられます。
また、マスキング自体も単に名称を隠せば良いという単純作業ではありませんので、担当従業員が自分の判断でマスキングしただけで利用できるという社内ルールは適切ではないと思われます。
WordやPDFといったデータファイルを読み込むことができる生成AIもあり、機密情報を削除したファイルと思って読み込ませたところ、実はそれが機密情報の記載されたままのファイルだったりすることもあり得ますから(ファイルタイトルは「マスキング版」だが実際はマスキングしていない生データファイルだった、というファイルタイトル間違いのケースなど)、ケアレスミスによる情報漏えい事故が起こることは容易に想定できます。
そのため、企業が業務において生成AIを使用する際には、情報漏えいをいかに防止するかを慎重に検討する必要があります。
そして、生成AIを業務で利用することは一律禁止することが、最も安全といえます。
しかし、今後生成AIを全く使用せずに業務を行うことは、現実的ではありません。
そのため、機密情報が記載されているものは生成AIに使用しないというような社内ルールを定め、それを徹底することが必要です。社内ルールについては、その情報を生成AIに入れて利用するメリットと、その情報について生成AIを使わないことで得ることのできる安全(生成AI利用により発生するかもしれないデメリットの予防)の線引きをどこにするかの企業判断(経営判断)が必要になります。
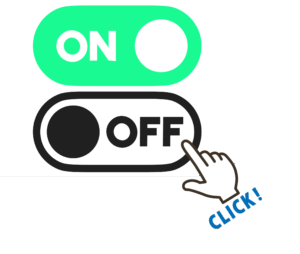
なお、少なくともChatGPTを業務で使う場合は、「学習機能」を「OFF」にして利用すべきで、もし「ON」にしていたら、「OFF」にして利用した方がよいと思います。このように生成AIを利用する際に、データをそのまま利用してよいか、マスキング等の加工をすべきか、生成AIに入れてはいけない情報を社内ルールでどのように定めるか等は、重要な問題ですが、利用者の判断にゆだねられている状態ですので、生成AIを業務で利用する際は、十分にご注意ください。
3 契約書を生成AIに読み込ませる際の注意点
契約書のリーガルチェックに特化した生成AIは少し前からありましたが、業務で使用するだけの高性能なものは料金が高額で、気軽に利用することができない状況でした。
しかし、最近のChatGPTやGeminiなどの無料で利用することができる生成AIも、性能が向上したことによって、契約書のリーガルチェックを行うことができるようになってきています。
また、作成したい契約書の概要を入力することで、定型的な契約書を作成することもできるようになっています。
そうすると、契約書作成やリーガルチェックを、わざわざ費用をかけて弁護士に依頼する必要がないと思われる方もいるかもしれません。
しかし、生成AIが契約書作成やリーガルチェックを行う際は、一般的・抽象的な観点でなされ、個別かつ具体的な事情を考慮することは難しいとされています。
個別かつ具体的な事情を生成AIに入力すれば、ある程度考慮されることはありますが、すべての事情を入力することは現実的ではありませんし、情報漏えいの観点からも好ましくありません。
そうすると、定型的な契約書であれば生成AIで対応することも可能といえますが、特殊な内容が含まれる契約書には生成AIで対応することはできないということになります。
このような場面では、生成AIではなく、弁護士に契約書作成やリーガルチェックを依頼する必要があり、適切であるということになります。
もっとも、生成AIを契約書作成やリーガルチェックで使用することで、たたき台として利用したり、見落としを防いだりすることができます。

当事務所でも、株式会社LegalOn Technologiesの「Legal Force」を導入して、契約書業務を行っております。吉田総合法律事務所は完全に守秘が確保できる契約内容で「Legal Force」を業務品質向上のために利用していますので、ご依頼者にも安心していただける状態になっています。
つまり、生成AIの特徴を理解したうえで、上手く使用することが重要ということになります。
4 契約書作成やリーガルチェックでお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください。
ことわざにも「ただほど高いものはない」というものがありますから、企業はビジネスの機密情報が記載されている契約書については、ChatGPTなどの生成AIではなく、契約書審査の実力が十分にある企業法務弁護士に、得ようとする価値に対応するコスト(料金)を支払って、高付加価値のリーガルチェックをしてもらう方が、結果的にビジネスには良い結果をもたらすのではないでしょうか。
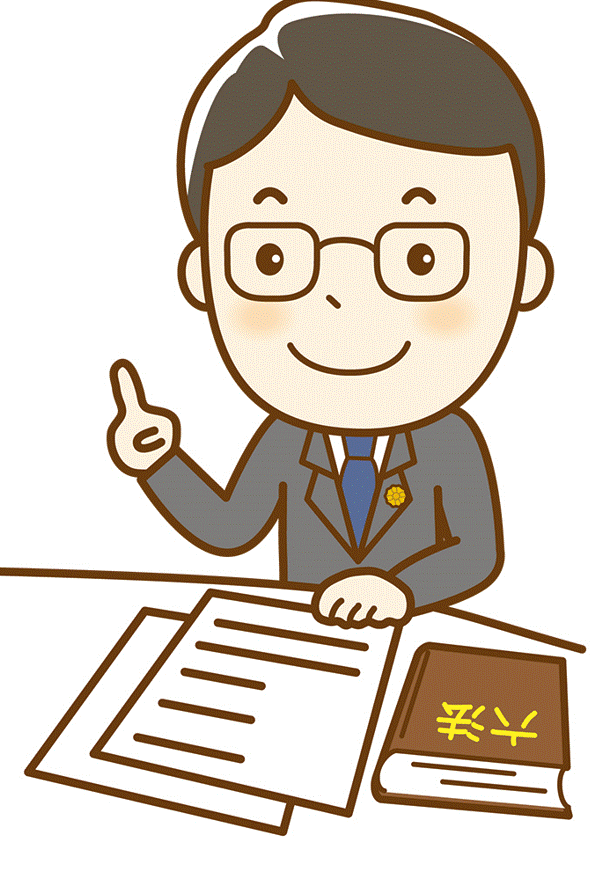
契約審査をご希望の企業様は是非、吉田総合法律事務所に契約書審査をご依頼されることをお勧めいたします。