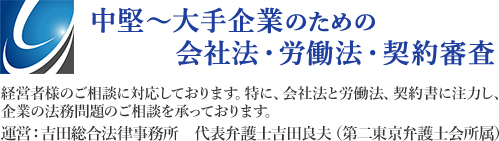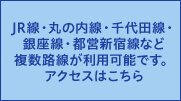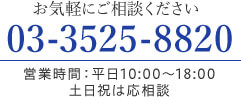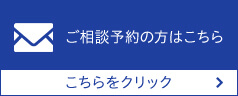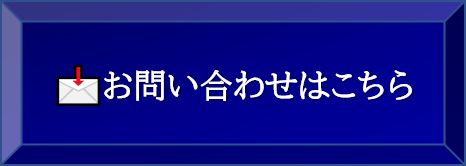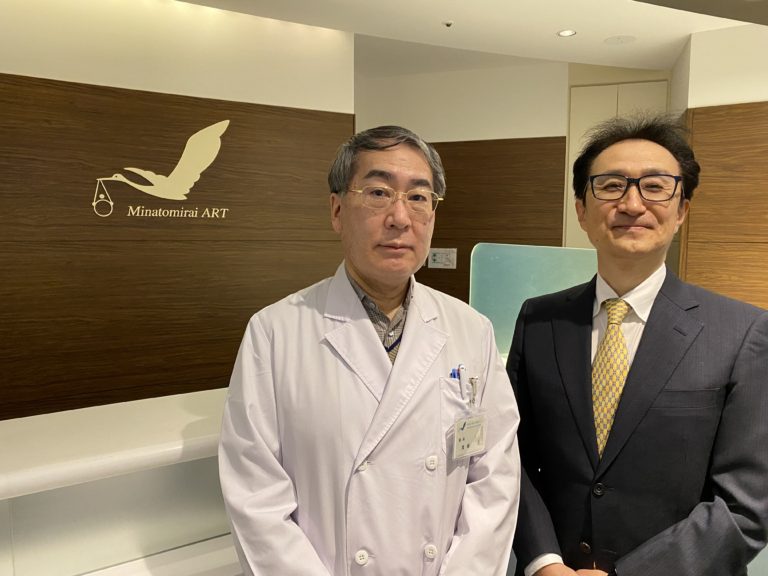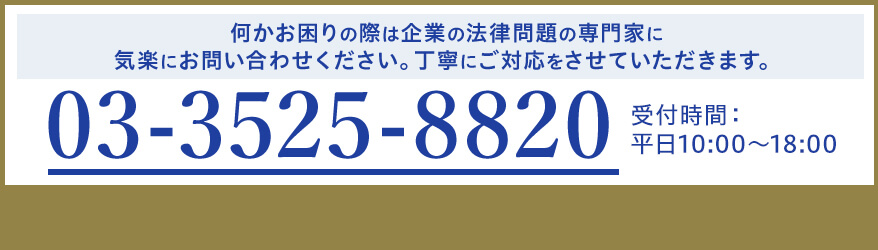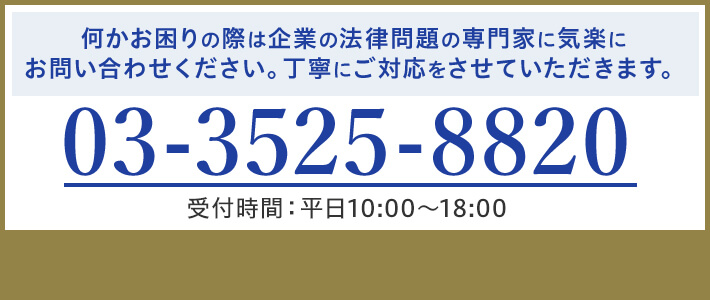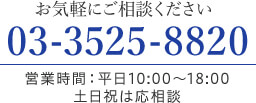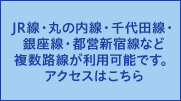| 【目次】 1 非上場企業における事業承継(親族外承継)とは 2 事業承継のプラン作成 3 後継者への株式譲渡の手続き 4 自己株式の取得や従業員持株会の活用 5 親族外承継による事業承継における相続争いのリスクM/a> 6 弁護士による後継者へのサポート 7 親族外承継による事業承継の解決事例 8 非上場企業の事業承継でお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください! |
1 非上場企業における事業承継(親族外承継)とは
事業承継は、中小企業白書において一つのテーマとして取り上げられていることからも分かるとおり、非上場企業のほとんどである中小企業や中堅企業が抱える問題といえます。
そして、非上場の中小企業・中堅企業における事業承継は、オーナー社長による親族内承継が多いと考えられてきました。
しかし、帝国データバンクの「全国『後継者不在率』動向調査(2024年)」によれば、2024年に行われた事業承継では血縁関係によらない役員・社員を登用した「内部昇格」による事業承継(いわゆる「MBO(マネジメント・バイアウト)」)が全体の36.4%に上昇し、同族承継(32.2%)よりも多いという結果になりました。
帝国データバンクの上記動向調査は上場企業も対象に含まれていますが、日本の中小企業の割合は99%以上ですので、非上場の中小企業においても、親族外承継による事業承継が増加していると考えられます。
親族外承継による事業承継において、適法な手続きを履行しなければ後継者が経営権争いに巻き込まれてしまうリスクが発生しますし、事業承継を行った元社長の相続争いに巻き込まれてしまうこともあり得ます。
したがって、親族外承継による事業承継も、弁護士による法的サポートを受ける必要性が高い分野です。
本記事では、非上場企業の親族外承継による事業承継について、弁護士が行う法的サポートを解説いたします。なお、親族内承継についてはこちらの記事で解説しておりますので、併せてご覧ください。
2 事業承継のプラン作成
事業承継を行うためには、最初に事業承継の計画を立てる必要があります。
具体的には、後継者は誰にするのか、どのような方法で経営権(支配権)を移転させるのか、などのことを検討して計画を立てる必要があります。
その際の重要なポイントは、後継者が安心して経営を続けることができるように、経営権(支配権)を確保させるということです。
事業承継というと税金(相続税等)対策に主眼が置かれることも多く、後継者が十分な経営権(支配権)を確保できない状況になってしまうケースも残念ながら存在します(特に株式数15%未満による配当還元方式を採用する事例で起こりやすくなります。)。このようなケースでは、後継者が株主総会での議決権数が少なくなり経営権争いに敗れて会社から追い出されてしまったり、経営権争いのストレスで心身が疲弊して(又は病気になり)自ら経営から退いてしまったりしてしまうこともあり得ます。このような状況になってしまっては、事業承継を行った元社長も後悔することになってしまいます。
そのため、事業承継では、最初に優先的に得るべき事項は後継者に十分な経営権(支配権)を持たせることで、その次に税金対策を検討することが適切と考えております。

もっとも、事業承継の当事者となる現社長や後継者にとって税金対策は常に重大問題です。吉田総合法律事務所では、事業承継に精通した会計事務所や税理士と連携して、事業承継の問題に対応しております。
3 後継者への株式譲渡の手続き
後継者に会社の経営権(支配権)を確保させるためには、現社長が後継者に株式を譲渡することが一般的です。
非上場企業では、株式の譲渡を制限しており、取締役会で承認しなければ株式の譲渡を行うことができないこととされていることがほとんどです。
この場合、現社長から後継者に株式を譲渡する株式譲渡契約書を作成していても、会社法で定められた取締役会の承認決議等の手続きを適切に行っていないと、後で株式譲渡が無効となってしまうリスクがあります。
そのため、会社法で定められている手続きを適切に行い、書類を作成して証拠化することが重要です。その際には、会社法に精通している弁護士からの法的サポートを受けると安心です。
また、後継者に適切な経営権(支配権)を確保するために、または、事業承継後に安定した経営を行うために、分散した株式を少数株主から買い集めることもあります。
この場合に、疎遠となっていた親族の少数株主が株式の買取に応じてくれず、交渉が難航してしまうケースは多々あります。
このようなケースでは、弁護士が代理人として少数株主と交渉すること、または交渉する方のバックアドバイザリーとして軍師的活動をすることは有益です。
なお、親族外承継の一つとしてMBO(マネジメント・バイアウト)があります。

MBOとは、会社内部の取締役が株式を買い取ることにより経営権(支配権)を取得することを意味します。MBOという言葉は、上場会社が上場廃止をする際のニュースで目にすることが多いですが、非上場会社の事業承継でもMBOはかなり増えているというのが実感です。
なお、株式譲渡については、こちらの記事もご覧ください。
4 自己株式の取得や従業員持株会の活用
親族外承継でネックとなる問題として、後継者の資金調達があります。
親族外承継の典型例として、取締役の一人が後継者となる場合がありますが、後継者である取締役の役員報酬が多くなく、株式買取の資金を用意できないこともあります。
また、中小企業においては、会社名義の資産(不動産など)が少なく、現社長個人名義の資産を会社の事業に使用していることもあります。この場合、事業承継の際には、現社長個人名義の資産も後継者または会社に移転させる必要があり、この場面においても後継者の資金力が求められます。
このような後継者の資金力の問題によって、現社長が保有している株式の全てや、経営権(支配権)確保のために必要な株式を後継者が譲り受けることができない場合があります。
この場合には、できる限り後継者が株式を譲り受け、残りの株式については自己株式の取得や従業員持株会を活用することによって後継者が経営権(支配権)を確保できるようにすることを検討します。

自己株式の取得で会社に帰属した株式は議決権がありませんので(会社法第308条2項)、自己株式の取得を行うことによって、後継者の議決権割合を相対的に高くすることができます。
なお、自己株式の取得については、こちらの記事もご覧ください。
また、従業員持株会は、後継者が従業員から支持を得ている場合には、後継者と従業員持株会が保有する株式によって経営権(支配権)を確保することもできます。また、従業員持株会が保有する株式を、議決権のない種類株式(この場合は議決権はないが優先配当株式にして経済的なインセンティブを付与することが有益です。)とすることによって、後継者の議決権割合を相対的に高くすることができます。
なお、従業員持株会については、こちらの記事もご覧ください。
このように、対象となる会社の具体的な状況や株主構成に応じて、自己株式の取得や従業員持株会の活用を検討することになります。

なお、自己株式の取得については、会社法で厳格な手続きが定められており、その手続きを行っていないと、自己株式の取得は無効となってしまいます。しかし、非上場企業の中には、会社法が手続法であること、特に自己株式の取得は手続きが複雑であることを理解せずに、当事者間の合意だけで自己株式を取得したことにしている企業がいらっしゃいます(しかしこれでは自己株式の取得は無効になります。)。
この場合には、本来の株主構成とは異なる議決権数で株主総会を行うことになり、株主総会決議の効力にも影響があることが少なくありません。そうなりますと、将来の話である事業承継が暗礁に乗り上げてしまうだけでなく、目の前の経営についてもいざこざが起きてしまい、経営権(支配権)争いになってしまうリスクすらあります。
そのため、自己株式の取得についても弁護士から法的サポートを受けることをお勧めいたします。
5 親族外承継による事業承継における相続争いのリスク
親族外承継では、親族内承継と異なり、事業承継を行う現社長の相続問題は生じないと捉えられてしまうことがあります。
確かに、親族外承継では相続問題が生じる可能性は低いですが、ゼロではありません。
親族外承継をした場合においても、相続人から後継者に対して遺留分侵害額の請求(民法第1046条)がなされることがあります。
具体的には、社長から後継者に対し株式を贈与(0円で譲渡)した後1年以内に社長が無くなってしまった場合、この株式の贈与が遺留分の対象となってしまいます(民法第1044条1項)。また、贈与(0円で譲渡)ではなく、後継者が一定の金額を株式の対価として社長に支払った場合(株式の売買)であっても、支払った金額が「不相当」な場合にも、遺留分の対象となることがあります(民法第1045条2項)。
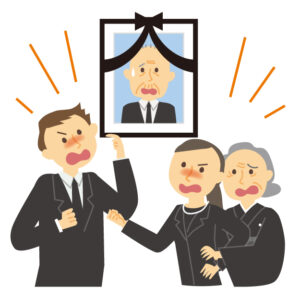
このように、親族外承継であっても相続の問題が生じてしまうリスクがあります。
そのため、親族外承継の計画を立てる際には、相続問題のリスクも含めて検討する必要があります。その際には、法律の専門家である弁護士から法的サポートを受けることが重要です。
なお、事業承継と遺留分についてはこちらの記事で解説していますので、併せてご覧ください。
6 弁護士による後継者へのサポート
事業承継は、現社長から後継者へ経営権(支配権)を移転しただけ完結するものではありません。後継者がスムーズに事業を承継して、継続・発展していくことが、事業承継の最終的な目標といえます。
後継者が会社経営の豊富な経験を有している場合もありますが、会社経営の経験が少ないために初めはサポートを受けながら経営を行っていくこともあります。

会社経営には会社法や民法の知識が必須ですが、日々の業務に追われてしまい、なかなか手が回らないということもあります。
そこで、後継者が法律の専門家である弁護士から会社法や民法に関するサポートを受けることが有益となります。
7 親族外承継による事業承継の解決事例
当事務所ではこの類型は比較的多いです。
経営権紛争を経て新しい経営体制(親族外承継)になり、年数を経て社内から新経営者が選ばれ、この記事でご紹介した手法を複数組み合わせるなどして無事に新経営体制として経営承継された会社様もいらっしゃいますし、創業者が、ご自分の子息子女様ではなく、社内の取締役に無事に経営承継された事例もあります。
当事務所は案件受注目的で経験をしていない事例について経験豊富などの記載はしませんので、「経験が無い法律事務所に依頼をして大丈夫だろうか?」などというご心配は不要です。
他方で、案件についての具体的事情はケースバイケースですから、他社の個別事例を知っても自社事業承継のお役には立ちませんし、何よりお客様のことを記載することはできませんので、記載はこの程度に止めさせていただきます。
8 非上場企業の事業承継でお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください!
事業承継というと、会計事務所や税理士事務所への相談を思い浮かべることが多いかもしれません。
しかし、事業承継は多くの法律問題が複雑に絡み合っており、法律問題を一つ一つ検討していかなければ、適切かつ有効な事業承継を行うことはできません。
そのため、事業承継は、会計事務所や税理士事務所だけでなく、法律の専門家である弁護士から法的サポートを受けることが大切です。
また、これらの法的サポートは会社の顧問弁護士が対応できる領域とは限りません。会社の顧問弁護士には通常業務の法的サポートをしてもらい、事業承継は特殊な領域ですからそれに適した弁護士を活用されることがよいと思います。
吉田総合法律事務所は、非上場企業の中小企業・中堅企業の事業承継にも力を入れており、ご相談を受け付けております。

事業承継でお困りの非上場企業は、吉田総合法律事務所へご相談ください。
吉田総合法律事務所へのご相談は、こちらのお問い合わせフォームからお願いいたします。