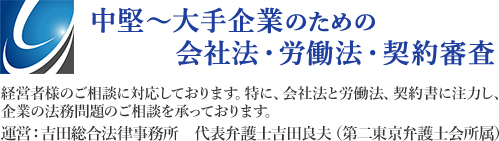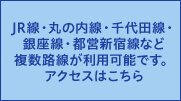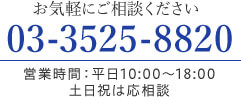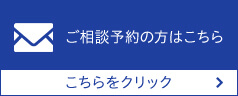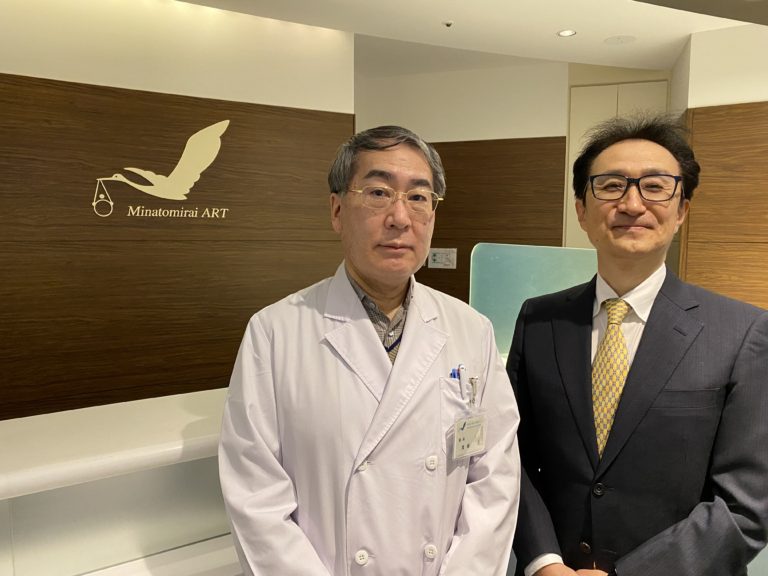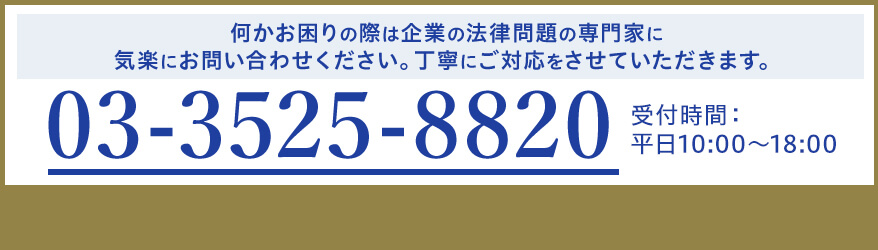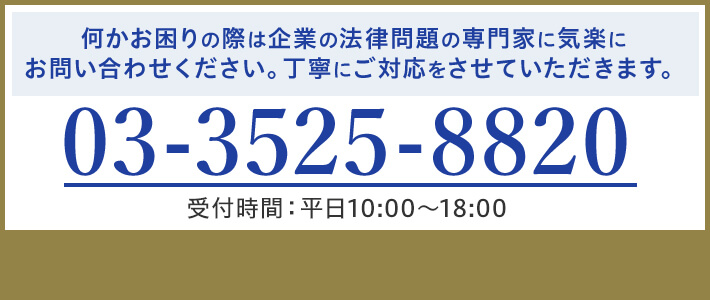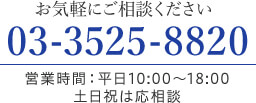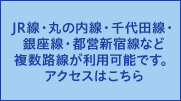| 【目次】 1 新たな類型のハラスメントに関する改正法が成立しました 2 2025年改正の概要とは? 3 カスタマーハラスメント(カスハラ)とは? 4 求職者等に対するセクシャルハラスメント(就活セクハラ)とは? 5 治療と仕事の両立支援の推進について 6 労働施策総合推進法等の2025年改正への対応でお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください! |
1 新たな類型のハラスメントに関する改正法が成立しました
2025年6月4日に、ハラスメントに関する改正法が成立しました。そして、同年11日に公布され、公布の日から1年6か月以内に施行されることになっています。
この改正法は、労働施策総合推進法と男女雇用機会均等法等を改正するもので、これまでは法律で明確に定められていなかったカスタマーハラスメント(カスハラ)や求職者等に対するセクシャルハラスメント(就活セクハラ)について、事業主に対策を行うことを義務付けるものとなっております。
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントについては、すでに法律で定められておりますが、労働者からハラスメントの相談・申告がなされてトラブルとなるなど、対応に苦慮することが多い問題です。
今回の改正法は、ハラスメントの新たな類型を追加するものであり、事業主の負担は少なくありません。
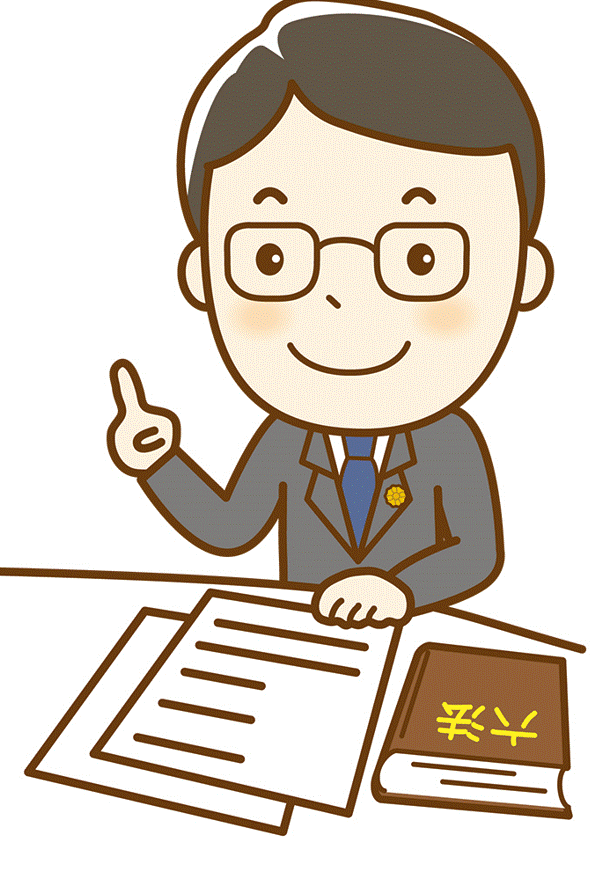
しかし、対応を怠ると、トラブルがさらに大きくなってしまい、事業主の責任が問われるリスクがありますので、対応が必須となります。
本記事では、ハラスメントに関する労働施策総合推進法等の2025年改正の概要について、解説いたします。 なお、本記事は厚生労働省が公表している資料を参考にしています。そのため、厚生労働省の公表資料もご参照ください。
2 2025年改正の概要とは?
労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法の2025年改正の内容は、大きく分けて次の3つです。
- カスタマーハラスメント(カスハラ)に関するもの
- 求職者等に対するセクシャルハラスメント(就活セクハラ)に関するもの
- 治療と仕事の両立支援の推進に関するもの
パワーハラスメント(パワハラ)については労働施策総合推進法で、セクシャルハラスメント(セクハラ)やマタニティハラスメント(マタハラ)については男女雇用機会均等法等で、これらの防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務であることが定められていました(なお、パワハラについてはこちらの記事 、セクハラについてはこちらの記事もご覧ください。)。
労働施策総合推進法等の2025年改正は、これらに加えて、カスハラや就活セクハラについても防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務とするものになります(上記①及び②)。
また、多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るために、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが事業主の努力義務となります(上記③)。
いずれも、事業主に対して必要な措置を講じることを義務付けるものであり、上記①及び②についてはこれを怠った場合には、厚生労働大臣による勧告の対象となります。そして、この勧告に従わなかった場合には公表されます(労働施策総合推進法42条2項)。
そのため、事業主としての適切な対応が必須となります。
そこで、上記①~③について、ポイントを見ていきます。
3 カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?
⑴ カスハラの定義について
対象となるカスハラについて、下記の定義が定められました(労働施策総合推進法33条1項)。
- 職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(顧客等)の言動であって、
- その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
- 当該労働者の就業環境が害されるもの。

そのため、カスハラと疑われる問題が発生した場合には、この定義に該当するかを判断することになります。
なお、カスハラについては、本改正法よりも前に、厚生労働省がマニュアルを作成しており、その中でカスハラの定義付けもしています。もっとも、これは厚生労働省が独自に作成したものですので、今後は、労働施策総合推進法33条1項の定める定義によることになると考えられます。厚生労働省のマニュアルに関してはこちらの記事 もご覧ください。
⑵ 義務付けられる雇用管理上の必要な措置
事業主は、カスハラを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません(労働施策総合推進法33条1項)。
また、労働者がカスハラの相談を行ったことなどを理由として、当該労働者に対して解雇などの不利益な取扱いをしてはいけません(同条2項)。
そして、他の事業主からカスハラ防止のために雇用管理上必要な措置について必要な協力を求められた場合には、これに応じる努力義務が課されています(同条3項)。
なお、これらの具体的な内容については、厚生労働大臣が指針を定めるものとされております(同条4項)。
そのため、事業主は、今後公表される指針に基づいて、対応を検討する必要があります。
4 求職者等に対するセクシャルハラスメント(就活セクハラ)とは?
⑴ 就活セクハラの定義について
対象となる就活セクハラについて、下記の定義が定められました(男女雇用機会均等法13条1項)。
- 求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(求職者等)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(求職活動等)において行われる、
- 当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により、
- 当該求職者等の求職活動等が阻害されるもの。
そのため、就活セクハラと疑われる問題が発生した場合には、この定義に該当するかを判断することになります。

⑵ 義務付けられる雇用管理上の必要な措置
事業主は、就活セクハラを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません(男女雇用機会均等法13条1項)。
また、労働者が就活セクハラの相談に対応したことなどを理由として、当該労働者に対して解雇などの不利益な取扱いをしてはいけません(同条2項)。
なお、これらの具体的な内容については、厚生労働大臣が指針を定めるものとされております(同条3項)。
そのため、事業主は、今後公表される指針に基づいて、対応を検討する必要があります。
5 治療と仕事の両立支援の推進について
2025年改正では、治療と仕事の両立支援のために必要な措置を講じることが、事業主の努力義務と定められました(労働施策総合推進法27条の3第1項)。
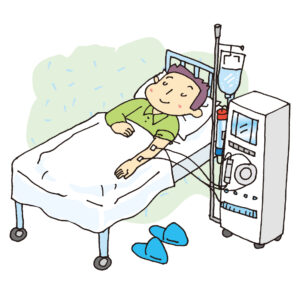
具体的な内容については、厚生労働大臣が指針を定めるものとされており(同条2項)、現時点では詳細が分かっておりません。
そのため、今後公表される指針に注意する必要があります。
6 労働施策総合推進法等の2025年改正への対応でお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください!
労働施策総合推進法等の2025年改正は、対象となる事業主に限定がありませんので、全ての事業主が対応しなければなりません。
また、対応していなかったり、不十分であったりする場合には、厚生労働大臣から勧告を受けたり、公表されたりしてしまいます。
さらに、事業主としての義務を怠ったとして、ハラスメント被害者から損害賠償請求されるリスクも発生してしまいます。

そのため、弁護士等からアドバイスを受けながら、改正法への対応を検討する必要があります。
労働施策総合推進法等の2025年改正への対応でお困りの企業・経営者は、吉田総合法律事務所の弁護士へご相談ください。