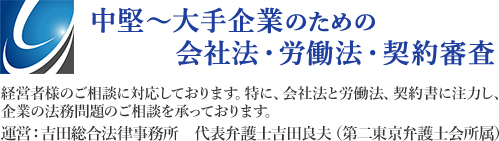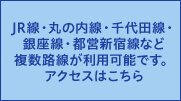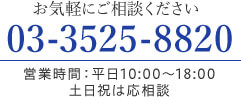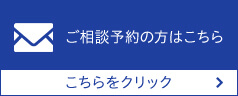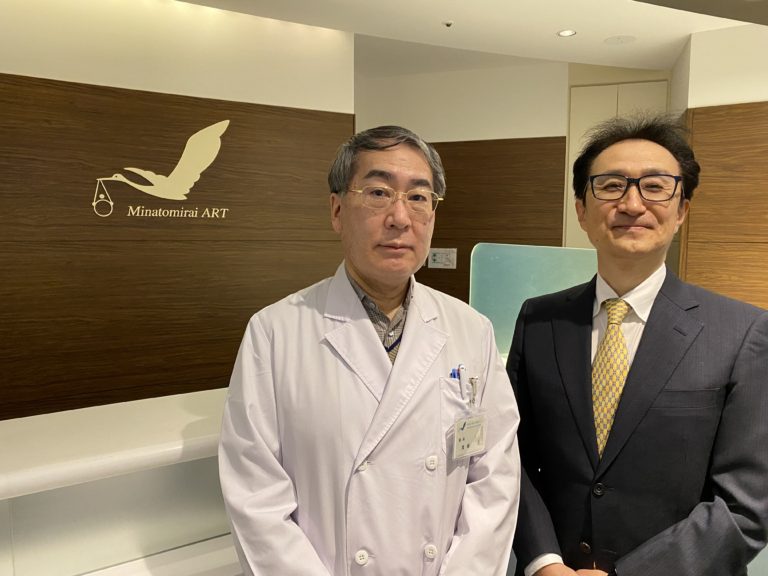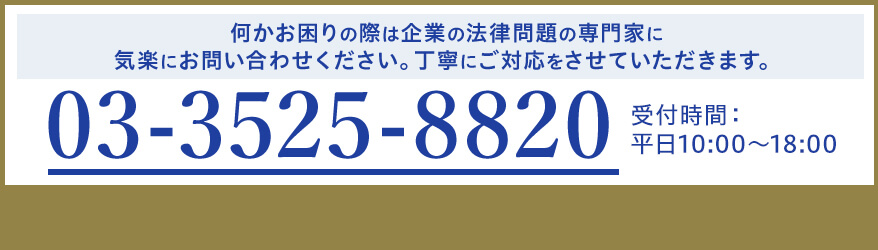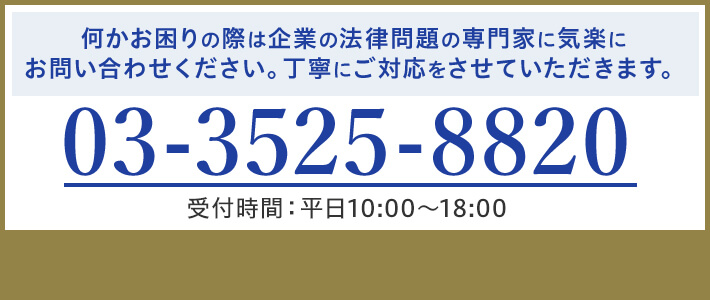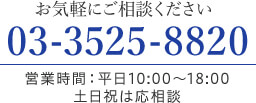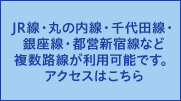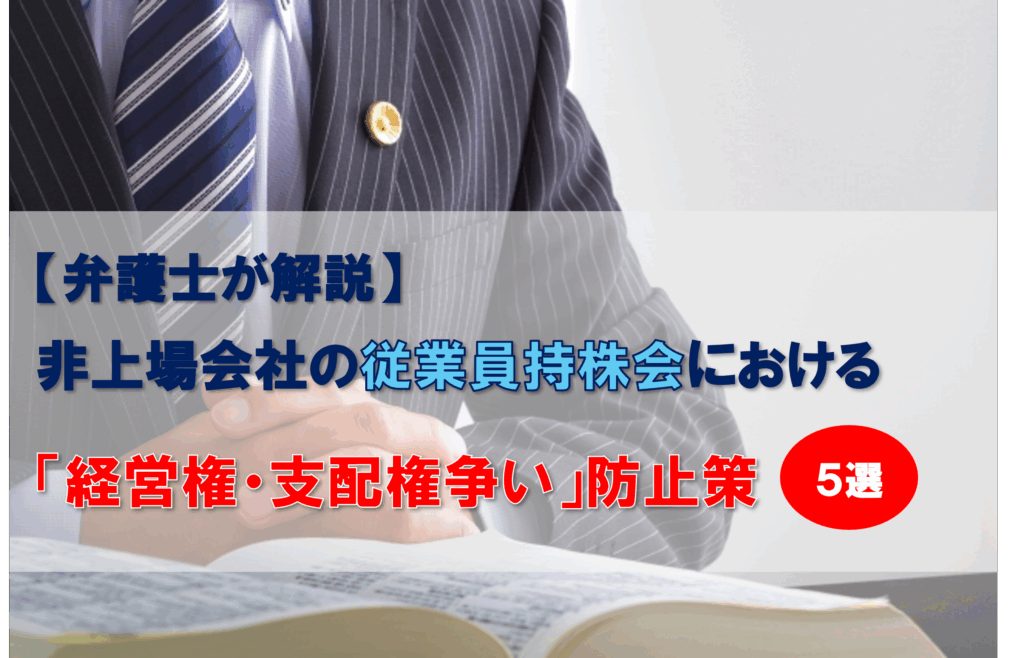
| 【目次】 1 従業員持株会は会社組織の一部ではない!? 2 従業員持株会と対立しないための対策とは? 3 従業員持株会規約を改訂するよりも最初から定めておく 4 従業員持株会でお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください! |
1 従業員持株会は会社組織の一部ではない!?
従業員持株会がある会社の社長や役員の方々は、従業員持株会は会社組織の一部であると思われている方も少なくないのではないでしょうか。
従業員持株会の多くは、会社の経営側が主導して設立されることや、会員が会社の従業員であることなどから、そのように認識することも当然かもしれません。
しかし、従業員持株会と会社の関係を法的な観点から見ると、その認識は誤りです。
従業員持株会は、通常は民法上の組合として設立されますが、会社内の組織ではなく、会社とは別の団体となります。
そして、従業員持株会は、自らが定めたルールである従業員持株会規約に従って運営されることになりますので、従業員持株会の外にいる会社の社長や役員に従う必要はないということになります。
そのため、従業員持株会と経営側との間で経営権・支配権のトラブルが発生し、会社経営が混乱してしまうということも、あり得る、ということにご注意ください。つまり、会社の経営権・支配権が従業員持株会の中心人物と現在の経営者との対立構造として問題になるという意味です。
従業員持株会を活用する理由の一つに、経営の安定化を図ることがありますが、上記のように従業員持株会があることによって逆に経営権・支配権争いの原因となってしまうこともあります。
これでは本末転倒ですので、従業員持株会を活用する場合には、経営権・支配権争いが生じないようにする必要があります。
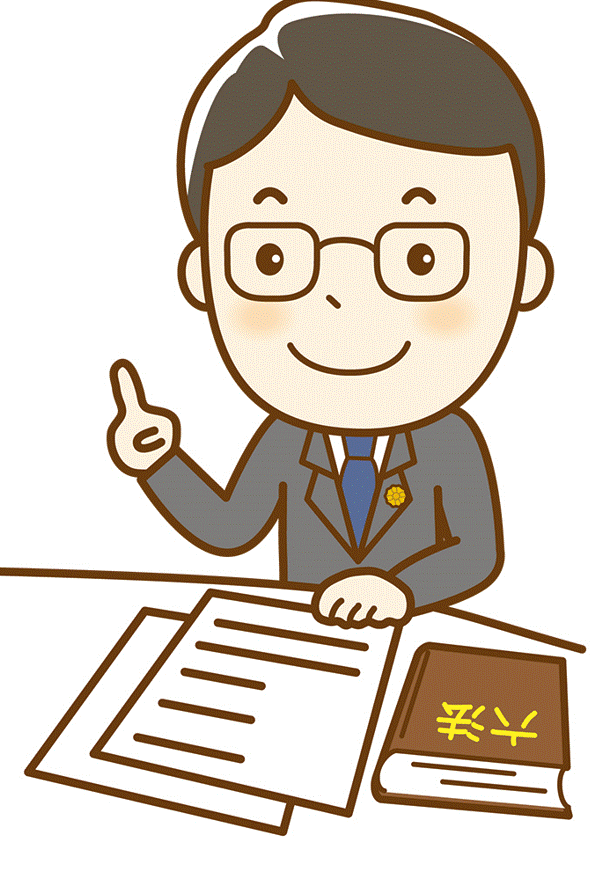
本記事では、非上場会社(中小企業・中堅企業)が従業員持株会を活用する際に、経営権・支配権争いを防止するための方法について解説します。
なお、上場企業における従業員持株会については日本証券業協会が作成した「持株制度に関するガイドライン」 がありますが、本記事ではこのガイドラインの対象ではない非上場企業を前提にしています。
2 従業員持株会と対立しないための対策とは?
上記1のとおり、従業員持株会は自らが定めるルールである従業員持株会規約にのみ従うことになりますので、会社や経営側の指図に従う必要はありません。
法的に従う必要がなくとも、事実上社長の指示に従って従業員持株会を運営するということはありますが、これはあくまでも従業員持株会が自主的に社長の指示に従っているということになります。
他方で、従業員持株会は従業員持株会規約に従わなければなりませんので、会社や経営側が一定の指図等を行うことができると従業員持株会規約に定めれば、従業員持株会はこれに従わなければならないということになります。
そのため、会社と従業員持株会との間で経営権争いが生じないようにするためには、あらかじめ従業員持株会規約に適切な定めをしておくことが重要です。
また、会社法上認められている制度を利用することも有用です。

具体的な内容としては、下記の5つが考えられます。
下記の5つ全てに対応することが必須というわけではなく、会社の状況に応じて必要なものを選択することが良いのではないかと思われます。
① 理事長を会社の代表取締役社長とする
従業員持株会では、理事長を選出し、運営や管理も理事長が行うことがほとんどです。そして、株式名義に記載される名義も理事長とされますし、株式の管理も理事長に信託され、株主総会での議決権行使も理事長が行うことになります。
そのため、従業員持株会において理事長は非常に重要なポジションとなります。
理事長は、従業員持株会の会員の中から選出されることが多いと思われますが、会員でなければならないというわけではありません。これも従業員持株会規約で定めれば、会員でない人を理事長とすることも可能です。
その際に、会社の代表取締役(社長)が理事長となることを従業員持株会規約で定めることも可能です。
会社の代表取締役(社長)が理事長を兼任することで、従業員持株会の運営等を会社がコントロールすることができます。
② 会員が持分を譲渡する場合に取締役会の承認を要することとする
非上場会社のほとんどは株式の譲渡を行う際には取締役会(又は株主総会)の承認が必要であり、これは従業員持株会が株式を譲渡する際も同じです。
もっとも、従業員持株会の内部で行われる会員間の持分の移動については、取締役会の承認手続きは不要とされています。
そうしますと、経営側の意向に関わりなく会員間で持分の移動が行われ、経営側と反対の意見を持つ会員が多くの持分を持ってしまうことも起こり得ます。
その結果、経営側と反対の意見を持つ会員の意向に沿って従業員持株会の議決権が行使されてしまう可能性も生じます。
このことを回避するために、株式と同様に、持分の移転についても取締役会(又は株主総会)の承認を要する旨を従業員持株会規約で定めることが考えられます。
この定めにより、経営側の意向と異なる持分の移転を防ぐことが期待できます。
もっとも、持分の移転を制限することは、会員の投下資本の回収を制限することにもなりますので、持分の移転を制限することが公序良俗に違反するとして無効となってしまうリスクがあります。
株式譲渡の制限については、譲渡承認を得られなかった株主が株式の買い取りを請求することができる手続きが会社法で定められており、投下資本の回収が保証されています。
そのため、持分の移転を制限する場合にも、同様に、投下資本の回収の道を残しておく必要があるかもしれません。
③ 退職に伴い退会として持分を買い取ることとする
会員が株式の持分を持ったまま従業員持株会を退会することができると、少数株主権を行使されるなどして、経営に支障が出てしまいます。
特に、従業員持株会を退会するのは、会社を退職した時であることが多いため、会社と利害関係が無くなった株主が経営側と対立的になってしまうことがあります。
このような事態を防ぐために、従業員持株会規約において、会社を退職する際に従業員持株会も退会することとし、退会時に持分を一定額で買い取ることを定めておく必要があります。
この点につきましては、こちらの記事 でも解説しておりますのでご覧ください。
④ 従業員持株会の株式を議決権のない優先配当株式(種類株式)とする
従業員持株会が経営側と対立するのは、株主総会での議決権行使の場面です。
そのため、従業員持株会が議決権を持たせないとすることも経営権争いの防止に役立ちます。
会社法では、株式の内容を変えることができることとされており、その株式を種類株式と呼びます。
この種類株式として、株主総会での議決権のない株式というものが認められています。議決権のない種類株式を持つ株主は、株主総会で議決権を行使することはできません。
従業員持株会が保有する株式を、この議決権のない種類株式とすることで、従業員持株会を株主として認めつつ、経営に関与させないこととすることができます。
これは、従業員持株会の会員である従業員が経営への関与に関心がなく、専ら配当金を得て収入を増やすことに関心がある場合に受け入れられやすいものです。
また、さらに受け入れやすくするために、他の株主よりも多く配当金を受け取れる優先配当種類株式にもするということもあります。
この場合は持株会には、議決権のない株式にする代わりに、配当は他の株主より多く受け取ることができるという説明をすることも考えてよいと思います。
なお、すでに従業員持株会が保有している株式(普通株式)を、種類株式に変えるには、特別な手続きが必要となります。この点については、こちらの記事 で解説しておりますのでご覧ください。
⑤ 従業員持株会の会員を含めた従業員と良好な関係を築くことが最も重要
これまでに見た4つは、いずれも法的に経営権争いを防止するための手段として紹介しました。
他方で、経営側と従業員持株会との関係が良好であれば、そのような対策を取らなくとも、経営が不安定になることはありません。
そのため、上記の4つのような対策をとるか否かにかかわらず、従業員持株会の会員を含めた従業員との関係を良好に保てるように努力することが、最も重要なのではないかと考えております。
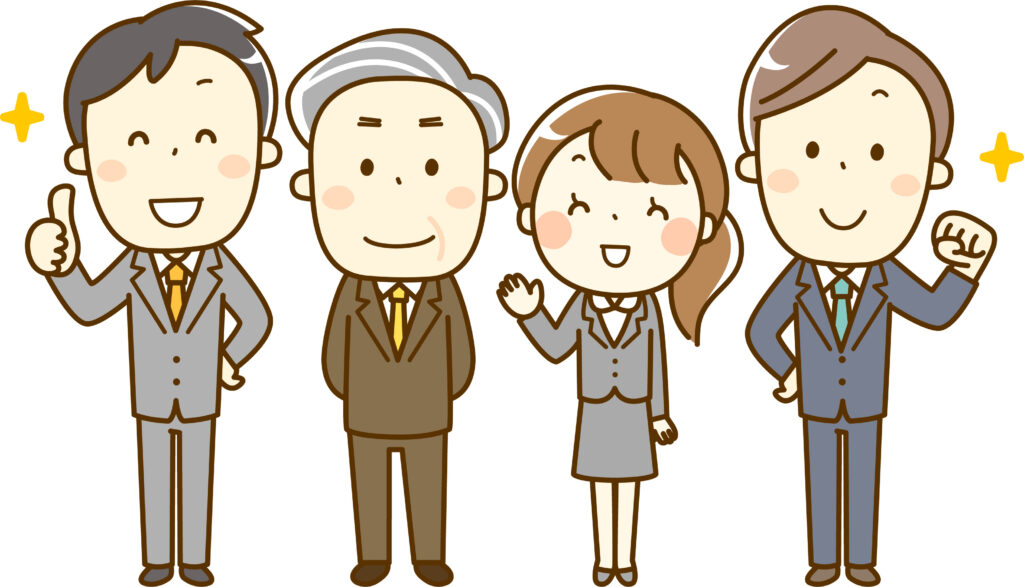
3 従業員持株会規約を改訂するよりも最初から定めておく
従業員持株会が民法上の組合である場合、従業員持株会規約は組合契約ですので、従業員持株会規約を変更する場合には原則として会員全員の同意が必要になります。
また、従業員持株会規約において改訂の手続きが定められている場合には、その手続きによって変更することができます。ほとんどの従業員持株会規約には改訂の手続きが定められていますので、それに従って上記2の対策を講じることが可能です。
もっとも、改訂の手続きでは、会員総会で過半数の承認が必要などとされており、すでに経営権争いが生じてしまっているような場合には、従業員持株会規約の改訂が行えないことになってしまいます。
また、経営権争いが生じていなくとも、これまでの内容から変わってしまうことについて心理的な抵抗を感じる会員もいるかもしれません。

そうしますと、従業員持株会を設立する時点で、最初から上記2の事項を従業員持株会規約に盛り込んでおくことが安全といえます。
もっとも、すでに従業員持株会がある会社も、経営権争いが生じる前であれば対応は可能と思いますので、なるべく早いタイミングで従業員持株会規約の改訂を検討されることをお勧めします。
4 従業員持株会でお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください!
従業員の福利厚生や経営者の節税、事業承継のために従業員持株会が利用されることが多くなっていますが、そこには思わぬ落とし穴が潜んでいるかもしれません。
特に、従業員持株会の会員は従業員であり、経営側から見ると会社内部の人間ですので、見過ごしてしまう可能性が高いといえます。
しかし、実際には経営権・支配権が争われてしまうリスクが潜んでおり、実際に経営権争いが発生してしまいますと、経営に甚大な影響が生じてしまいます。
それにもかかわらず、従業員持株会について参考となる書籍や情報は限られており、どのように対応すれば良いか分からないということもあります。
そのため、従業員持株会を利用する際には、弁護士のアドバイスを受けながら進めていくことが大切となります。
吉田総合法律事務所では、従業員持株会規約の内容や運営方法へのアドバイス、株式に関する会社法上の手続きのサポートなど、従業員持株会に関するご相談に対応しております。
従業員持株会でお困りの企業・経営者の方は、ぜひ吉田総合法律事務所へご相談ください。